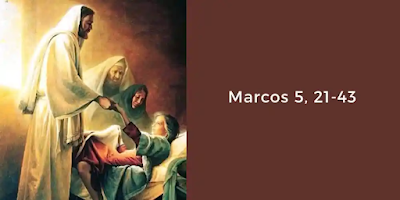季節の変わり目ですね。私は、多忙の睡眠不足もあってか、風邪をこじらせて一週間、人と会う仕事以外は寝たり起きたりとなっていました。忙しいときは「ずっと寝ていたい」と思いますが、病気で寝込むと「早く起きたい!」と身勝手なのが人間ですね。今日の聖書はイエス様が「起きなさい!」と言われている言葉を読みます。どんな意味があるのでしょうか?一緒に聖書を読みませんか?礼拝は明日は名古屋の復活教会で担当します。それをYouTubeで配信もします。お会いしましょう。YouTubeチャンネル登録はここから→Pastor Hirotaka Gabriel TOKUHIRO - YouTube
-----
聖書の言葉 マルコ5:21~43 (新70)
5:21イエスが舟に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まって来た。イエスは湖のほとりにおられた。 22会堂長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足もとにひれ伏して、 23しきりに願った。「わたしの幼い娘が死にそうです。どうか、おいでになって手を置いてやってください。そうすれば、娘は助かり、生きるでしょう。」 24そこで、イエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。
大勢の群衆も、イエスに従い、押し迫って来た。 25さて、ここに十二年間も出血の止まらない女がいた。 26多くの医者にかかって、ひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。 27イエスのことを聞いて、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。 28「この方の服にでも触れればいやしていただける」と思ったからである。 29すると、すぐ出血が全く止まって病気がいやされたことを体に感じた。 30イエスは、自分の内から力が出て行ったことに気づいて、群衆の中で振り返り、「わたしの服に触れたのはだれか」と言われた。 31そこで、弟子たちは言った。「群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに、『だれがわたしに触れたのか』とおっしゃるのですか。」 32しかし、イエスは、触れた者を見つけようと、辺りを見回しておられた。 33女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。 34イエスは言われた。「娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。もうその病気にかからず、元気に暮らしなさい。」
35イエスがまだ話しておられるときに、会堂長の家から人々が来て言った。「お嬢さんは亡くなりました。もう、先生を煩わすには及ばないでしょう。」 36イエスはその話をそばで聞いて、「恐れることはない。ただ信じなさい」と会堂長に言われた。 37そして、ペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネのほかは、だれもついて来ることをお許しにならなかった。 38一行は会堂長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、 39家の中に入り、人々に言われた。「なぜ、泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない。眠っているのだ。」 40人々はイエスをあざ笑った。しかし、イエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて、子供のいる所へ入って行かれた。 41そして、子供の手を取って、「タリタ、クム」と言われた。これは、「少女よ、わたしはあなたに言う。起きなさい」という意味である。 42少女はすぐに起き上がって、歩きだした。もう十二歳になっていたからである。それを見るや、人々は驚きのあまり我を忘れた。 43イエスはこのことをだれにも知らせないようにと厳しく命じ、また、食べ物を少女に与えるようにと言われた。
説教「あなたに言う。起きなさい」徳弘浩隆牧師
1、ゆっくり、寝ていたいのに…
「おきなさい!」という言葉は、だれでも聞き覚えがある言葉だと思います。特に思い出すのは、もっと寝ていたい時に親から言われる言葉です。「ちょっと、何時だと思ってるの?」「学校に遅れますよ」「オキナサイ!」と、だんだんとその口調が強くなるこの言葉、だれでも言われた事があるでしょう。または、言ったことがあるでしょう。
「ああ、もう、うるさいなぁ」「分かってるよ。もう少しだけ!」という自分の心の叫びも、だれでも覚えがあるでしょう。
今日の聖書は、イエス様と、二人の女性が出てきます。今日はこの二人目の方の女性の出来事に目を向けて、一緒に神様の呼びかけを聞いていきたいと思います。この女性は「起きなさい」と呼びかけられたからです。何が起こったのでしょうか?イエス様のその呼びかけは、それ以上にどんな意味を持っていたのでしょうか?一緒に見ていきましょう。
2,聖書
今日は先週の続きの、その次の出来事です。もう一度ガリラヤの側へ舟で戻られると、大勢の群衆がまた集まってきました。湖のほとりにおられると、ヤイロという会堂長の一人が来て、イエス様に願い出ました。「娘が重体なので来て祈ってほしい、きっと娘は助かり、生きるでしょう」と。
イエス様はそれに応じて一緒に出掛けました。しかし、そこに思わぬ出来事が起こります。別の女性の登場です。この女性も不思議な出来事とやり取りの末に癒されるのですが、そうしている間に、ヤイロの娘の死が知らされることになります。
何という事でしょう。ヤイロとしては、イエス様が向こう岸から帰ってこられ、お会いできて、お願いしてみたらイエス様が一緒に歩きだしてくれた。もう大丈夫だ、と彼は思ったでしょう。しかし、それが、思わぬ番狂わせで、その人には良かったけれども、自分の娘はそのせいで間に合わなかった、「亡くなりました」という知らせを受けたのです。「信仰深い」ヤイロの使いや、おそらくヤイロ自身も、これ以上イエス様を煩わせてはいけないと思いました。しかしそれは、「信仰深いことではありません」でした。そこが今日の大切なところだと心にとまります。
イエス様は「恐れることはない、ただ信じなさい」と言われたのです。もう、「手遅れの状況」なのにです。しかし、イエス様は家まで行かれ、「眠っているだけなのだ」と言われ、その娘の部屋へ行き、「起きなさい」と言われました。すると、その娘はすぐに起き上って歩き出したのです。
3,振り返り
今日は、「信仰深い」会堂長ヤイロやその使いのものが、死を受け入れてイエス様をこれ以上煩わせてはいけないと引き下がったことが信仰深いことではなかったという、皮肉な逆転がとても心に残ります。
「そのままを受け入れるのではなくて、まだ大丈夫、まだあなたと一緒に歩いていって、あなたの人生を解決してあげるのに」というイエス様のお気持ちを見ていなかったヤイロたちの謙虚さは、信仰深いではなくて不信仰だったという事から、神様の側の、人間の常識や思いを超えた計画を信じていくことへと促されています。
それが、「寝ているだけのヤイロの娘」に、そして、「信仰がまだ寝ているヤイロたちに」さえも、「さあ、起きなさい」と聞こえてくるのだと学ばされます。
それを学ぶために、今日の旧約聖書をもう一度見てみましょう。聖書の中の哀歌という珍しいところから選ばれています。哀歌の哀は、愛情の愛ではなくて、哀悼の哀です。これは、紀元前586年に起きたエルサレム陥落と神殿の破壊を嘆く歌で、バビロン捕囚の時代にかかれたと考えられ、預言者エレミヤの哀歌ともいわれています。
繁栄を極めたイスラエルという国も不信仰で、府には分裂し、その後、順にそれらの国が滅び、預言者の言葉通りにエルサレムの神殿も破壊され、人々はバビロンに強制連行されたというバビロン捕囚を経て、国を失い、流浪の民となったユダヤ民族の嘆きと哀しみを歌った歌です。
しかし、それは嘆きの言葉で終わってはいません。「主は、決してあなたをいつまでも捨て置かれはしない。主の慈しみは深く 懲らしめても、また憐れんでくださる。人の子らを苦しめ悩ますことがあっても それが御心なのではない。」と今日のところも結ばれています。
ヤイロも、イエス様のお力を信じ、お願いしてきてもらっているのに、目の前の状況が悪くなるとあきらめてしまいました。自暴自棄になったり、神を呪ったりはしませんでしたが、「信仰深い」彼は、イエス様にこれ以上来ていただくことは申し訳ないと、自分の判断で神様の介入を断り、止めてしまっていたのです。
しかし、イエス様は、それ以降も、それ以上の道のりも、一緒に歩いてくれて、解決をしてくれました。
4,勧め
私たちの人生にも、そんなことがあるでしょう。自分の不信仰ならまだしも、信仰があると思うからこその決断や行いが、神様のお働きを妨げているかもしれません。
「さあ、起きなさい」という言葉を、もう一度一緒に、新しい気持ちで聞いていきましょう。私の人生に、新しいことが起こるはずです。一緒に教会生活をしていきましょう。
----------------------
牧師コラム・ ずーっと寝ていたい!
私は最近、いそがしくて忙しくて、こう思っていました。「あー、もっとゆっくり寝ていたい」「仕事が山を越えたら、飽きるくらい寝てやる!」と。
すると神様はそれをかなえて(?)くれました。なんと、風邪をこじらせてしまって、起きられなくなってしまったのです。急いで食べれるだけ食べて、薬を飲んで、横になるとすぐ眠れます。熱があって汗をびっしょりかいて、目が覚めたらまた何かを食べて、寝て…というのを何度も繰り返しました。人と会う仕事の時はシャワーを浴びて少し小奇麗にして、それが終わるとまた倒れこむという日々でした。
そのうちこう思いました。「あー!寝てるのはもうたくさんだ。早く起きて、あれもしたい、あそこにも行かなきゃ」と。最初はゆっくり寝れるのに嬉しくもありましたが、そのうちは寝るのも飽きてきて、体が痛くて眠れなくなり、今度は、それを恨むようになりました。
なんと、人間は自分勝手なのでしょう。いそがしいと、「ずっと寝ていたいものだ」と恨みを言い、病気で寝込み続けることになると、「もうそろそろ、起きなさい!」と言われたいものだと、神様に恨み言を言うのです。
今日のイエス様は、「さあ、起きなさい」といわれました。すなおに、「はい!」と言いたくなりました(笑)
季節の変わり目、皆さんも元気にすごしてくださいね。